足の構造と問題点
足の骨格と構造
人間の身体は大きく5つのブロックに分かれています。足は図のように全身からみると小さなものですが、その2本の足で全体重を支え負荷が集中する部位で、 全身に影響をおよぼします。そんな大切な足に履くものが靴です。したがって靴の不具合は、単に足が痛いだけではなく頭痛や肩こり、腰痛などの原因になりま す。ここでは、シューズと特に関係が深い下肢の骨格構造を示しています。
<下肢の区分>
-
骨盤部 内臓を支える土台
-
上腿部 大腿骨
-
下腿部 脛骨、腓骨
-
足 部 くるぶしより下部
<足の骨>
人間の全身の骨の数は200あまり。「足」の骨の数は、通常、片足26個、小さな種子骨を加えると28個、左右で56個です。約4分の1もの骨が「足」の 骨なのです。体重を支え、歩き、走り、跳ぶなどのさまざまな動作を行うために、小さな骨がたくさん集まって体を支えているのです。
足の骨は大きく「足根骨」「中足骨」「指骨」3つのブロックに分かれています。
<足のアーチ>
人間は成長するにしたがい、個人差はあるものの3~4歳ごろから足にアーチが出現します。足のアーチには3つの機能があります。
-
足を蹴りだす力(バネ)
-
衝撃の緩衝(クッション)
-
足底の筋肉や神経の保護
足には大別し3つのアーチがあり、これらが連携して「おわん」の口を下においたようなドーム構造になっています。
内側縦(ないそくたて)アーチ
足の内側縦方向の一番大きなアーチ。一般的に「土踏まず」と呼ばれる部位。
(かかと~中足骨先端までの範囲)
外側縦(がいそくたて)アーチ
足の外側縦方向のアーチ。外見上はわかりにくいが小さなアーチ。
(かかと~中足骨先端までの範囲)
横(よこ)アーチ
中足骨部横方向のアーチ。

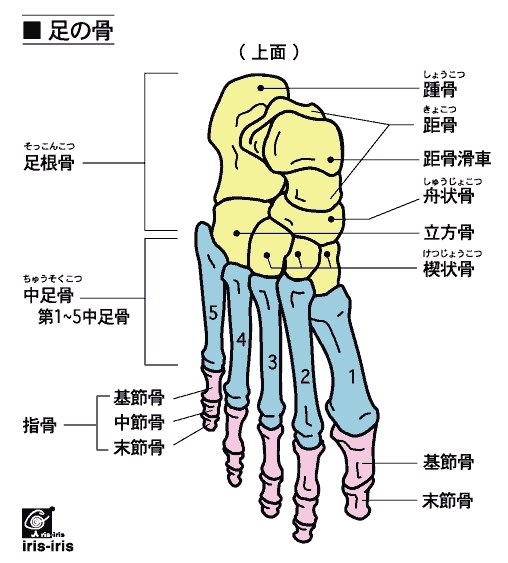


-
人間の体重は、足の内側に多くかかり、足底の筋が伸び、土踏まずが下がって、疲れやすくなります。
-
もともと足の骨は内側に倒れこみやすい構造になっています。アーチが過度に低下することをサポートするシューズの機能はたいへん重要です。
-
過度のスポーツによる疲労の蓄積、肥満、老化、遺伝などでアーチは低下します。アーチが低下すると、3つの機能が発揮しにくくなります。さらに外反母趾に代表されるような足部の変形障害にもつながってきます。間違ったシューズ選びもアーチの低下につながりますので正しいフィッティングを心がけましょう。
足の障害
足に関する病気や障害は数多くありますが、なかには、間違った靴選びや履き方、歩き方の習慣が原因となって引き 起こされると考えられるものもあります。反対に、それらの症状は、靴を替えたり、足をケアすることによって、緩和されたり、改善されたりすることがあるこ とも知っておきましょう。
アーチに関する代表的な障害
偏平足
アーチが低下することで、路面からの衝撃をやわらげる機能が衰えます。そのため身体へのダメージが増えて疲れやすく、足の力が出しにくいと言われています。
また踵骨の外反(内側への倒れこみ)をともなった場合は「外反扁平足(がいはんへんぺいそく)」と呼びます。スポーツによる疲労、長時間の立ち仕事やハイ ヒールなど負担のあるシューズを履くことによって発生することがあります。アーチサポートの施されているシューズや中敷によって負担を軽減します。
通常幼児期は、扁平足の状態ですが、成長と共に足のアーチが形成されていきます。

開張足
踏み付け部の足幅が広く、足が薄くなります。
そのため、足の裏・ゆび周辺に胼胝(タコ)ができやすくなります。
女性に多く見られるトラブルです。外反母趾を伴うケースが多いといえます。シューズでは、過度の倒れこみを防ぐ機能やアーチサポートの施された中敷によって負担を軽減します。
ハイアーチ(足のアーチが高すぎる状態)
足底やふくらはぎの筋、腱の柔軟性が乏しい人、あるいは足底の筋力が強すぎる人に多いと言われます。接地面積が少なく、かかとと前足部に圧力が集中するた め胼胝(たこ)が出来やすくなります。足当たりのやわらかい中敷やクッションの良いシューズの使用で、楽になる場合があります。
足首の内反と外反
身体の中心(へそ)を基準に、左右対称とし、「内外のどちらに反っているか」を指して内反、外反と呼びます



足形状の代表的な障害
外反母趾(がいはんぼし、Hallux valgus)とは、足の親指が小指の方に曲がっていく症状の総称。 足の横アーチが伸びたり、緩んでしまった上に靴など履物によって締め付けられることで結果、親指が小指側に曲り変形した状態。 足に合わない靴を履いている場合になりやすく、女性に多く見られる。
発生原因
-
外反母趾の発生原因は、靴によるものと足型など遺伝によるものが考えられます。
-
靴が原因となる場合は、つま先の細い靴、かかとの高い靴、大きすぎたり小さすぎたりサイズの合わない靴、さらに足のつま先形状と靴の形状が異なっている、などがあります。
-
足が原因となる場合は、かかとが内側に倒れ込んでアーチが低下している足(いわゆる外反扁平足)や趾が長い足、関節がやわらかく筋力も弱い足などがあります。
-

浮きゆび
立脚時、足趾が路面に接地せずに浮いた状態。横アーチの低下、開張足、外反母趾に伴って併発する ケースが多く、身体の姿勢保持力が低下しバランスがとりにくい為、腰痛や肩こり、ひざの痛みにも繋がります。小さすぎる靴、大き目の靴、ゆるめの脱げ易い サンダルなどを常用し、足趾を曲げて踏ん張る動きが少ない場合も足裏の筋肉やMP 関節の機能が低下し発生する度合いが高まります。成長過程の子どもの足に見られる場合もあります。
足趾のグーパー運動や五本ゆび靴下などで、足趾の動きを促し、正しくフィットした靴選びを行いましょう。
陥入爪かんにゅうそう
ツメが皮膚に食い込み(巻きヅメ)、炎症や化膿を起こした状態、やがてツメに接している皮膚の肥厚をきたす状態の総称。深ヅメ、つま先の狭い靴などで発生します。靴はつま先、横幅方向に余裕のあることが大切です。

胼胝たこ
皮膚が角質化した状態、つまり硬く厚みをもった状態のことをいいます。皮膚に圧迫や摩擦が局所的に繰り返されると、まず熱を持って水疱(いわゆるマメ)ができます。
その後、水疱が破れて皮膚が厚くなって胼胝が発生します。長時間の歩行やランニングでよく発生します。また、縦アーチや横アーチが低下して母趾球や小趾球が突出すると、その突出部でも発生します。
ケアとしては、入浴時など、皮膚がやわらかくなっているときに胼胝用のヤスリや軽石などで表面を削ります

鶏眼けいがん通称:魚の目
発生要因は胼胝と同様ですが、胼胝と異なるのは、胼胝は身体の表面、外に向かって皮膚が肥厚するのに対して、魚の目は、皮膚の内部に円錐状に進行します。
皮膚との境界がはっきりしているのも特徴です。皮下の神経に当たると痛みが発生します。
胼胝、鶏眼、共に圧力や摩擦を減少させることで予防(あるいは軽減)できます。例えばアーチサポートの施されている靴や適正サイズの確認、アッパーのやわらかい靴で負担を軽減します。

足底腱膜炎そくていけんまくえん
足底腱膜は踵骨底側の内側から前足部にいたる強靭な腱で、足アーチを支えながらバネの役割もしています。着地や蹴り出しの際、足趾が背屈すると、足底腱膜は引っ張られ足アーチが高くなります(ウィンドラス機構/巻き上げ現象)。
足底腱膜炎は、踵骨付着部や足底中央部で線維性組織の微細な断裂が生じて発生します。ランニングやウォーキングなど過度な運動が誘引となりますが、中年以降の肥満や老化で発生することもあります。
症状
足底腱膜の踵骨付着部に、歩行時に刺すような痛みがあり、朝の起きがけに痛いのが特徴です。つま先立ちやかかと接地時に痛み、踵骨足底の内側に圧通を認めます。
靴による予防と緩和
クッ ション性のよいシューズを履くことによって痛みを緩和しますが、時に松葉杖を使用し、局部への体重負荷を減ずることも必要となります。ヒールをアップした 靴にかかとの疼痛部を繰りぬいた靴の中敷が処方されることもあります。予防的には、足底腱膜のストレッチが有効とされています。
O脚とは
両足の内側をかかとからつま先までぴったり合わせて立つと、左右のひざに隙間ができる状態。ひざ内側への荷重が大きくなり、中高年の女性に多い変形性膝関節症が起こりやすくなります。
O脚の判定方法
両足の内側をぴったり合わせて立ち、両膝関節部の隙間に横にした状態の指が何本入るか確認します。2本以上入ればO脚の傾向あり。クッション性の良いシューズをおすすめしましょう。
X脚とは
両足をぴったりと合わせて立とうとすると、先に左右のひざが接触し、左右の内踝(うちくるぶし)間に隙間ができる状態。X脚はひざの外側にかかる荷重が大きくなり外反扁平足をともなう場合もあります。
XO脚
両ひざがつくけれど、すね(下腿骨)が外側にはみ出して湾曲している状態です。特にひざの外側の骨(腓骨小頭)が外に出ています。
大腿内転筋などひざをしめる力が強い若い女性に多く見られます。
